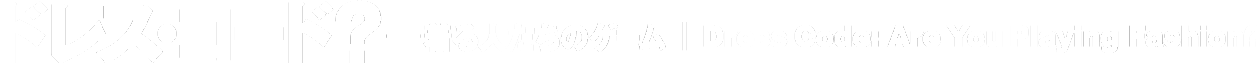キュレーターインタビュー
Curator interview
2020年8月30日まで開催中の「ドレス・コード?―着る人たちのゲーム」を企画した京都服飾文化研究財団の小形道正さんと、開催会場である東京オペラシティ アートギャラリーの福島直が、13あるコードに沿って、展示している作品や衣装をピックアップし、ポイントや見どころについてお話ししました。
- O=京都服飾文化研究財団 アソシエイトキュレーター:小形道正
- F=東京オペラシティ アートギャラリー キュレーター:福島直
- T=東京オペラシティ アートギャラリー 広報:市川靖子
展示風景画像 撮影:忽那光一郎
T:展覧会は13のコードに沿って展開されていますね。それぞれのコーナーごとに、二人がオススメしたい作品や「ここを見るべき!」というポイントをお話ししてもらえますか?
F:会場でまず最初に皆さんをお出迎えするのは「00. 裸で外を歩いてはいけない?」のボロきれの山に埋もれるヴィーナス像です。愛と美の女神ヴィーナスとボロボロの古着の対比は何をあらわすのか、ちょっと考えられるように一番最初に展示しています。
例えば今って流行に合わせて大量の服が消費される社会ですが、この作品では古着はたちまち芸術的価値が生まれています。もしも裸で公共空間にたたずむヴィーナスが生身の人間だったら……?! などなど、いろいろと考えてしまいます。

T:ドキっとしますよね。
F:この作品は展覧会のプロローグとして、展覧会のテーマでもある「着る」ということの根源的な意味や、私たちが生きる現代社会について様々な問いを投げかけていると思うんです。
T:確かに。いろいろな意味をはらんでいる作品ですね。次のコードは「01. 高貴なふるまいをしなければならない?」です。すごく古いドレスの後ろに、漫画でしょうか、イラストが2点、展示されていますね。右は女性ですが、左は男性?でも女性にも見えるような……。

O:これは私たちの財団が所蔵する18世紀後半に作られた実際の衣装と、フランス革命期を舞台にした坂本眞一の漫画『イノサン』『イノサンRouge』とのコラボレーションなんです。フィクショナルなポートレートがあることで歴史的な衣装も、実際どんな人が着ていたのかと想像できるのではないでしょうか。またマリー=ジョセフ・サンソン(左)とマリー・アントワネット(右)の、2人のマリーの生き様は、現代を生きる私たちにも深いつながりと共感を与えてくれると思っています。
T:やっぱり左のイラストに描かれているのは女性だったんですね。マリー=ジョセフ・サンソンは架空の登場人物ですが、フランス革命の頃に職業を持ち、男性の服を身にまとう、というのはまさに革命だったのでは。次のコーナーはズラっとスーツが並んでいますね。圧巻です。奇抜なスーツから、年代の古いスーツまでいろんな種類があるようですが。

O:これは本当にスーツ?というタイプもありますが、僕が一番注目して欲しいのは、戦後イギリスの男性ファッションを先導したバニー・ロジャースが着用したこだわりのスーツたちですね。のちに彼のスタイルはイギリスを代表するデザイナー、ポール・スミスによって「バニー・ロジャース・コレクション」として発表されているんですよ。
T:なるほど、デザイナーがデザイナーをリスペクトして踏襲する、ということもあるのですね。

F:次のコードは「03. 働かざる者、着るべからず?」です。
T:なんだかミシンのような機械音が聞こえてきますね。
F:現代はAIによって世の中が便利になる一方で、労働をAIにとってかわられることを危惧する側面もあると思います。大画面の映像は青山悟さんによる映像作品です。このミシンはコンピューターで制御されていて、暗がりで淡々と針を進めています。刺繍されているのは手仕事による労働の喜びを綴った、ウィリアム・モリスのテキストなんです。テクノロジーを象徴するミシンが、相対する手仕事についての言葉を紡ぐとき、労働観の問題が浮上することを意識せずにはいられなくなります。

T:私たちがこれまで手でしてきた仕事がいつかコンピューターにとってかわられるかもしれない。そう思うとなんとも言えない焦燥感がありますね。
「04. 生き残りをかけて闘わなければならない?」というちょっと挑戦的なコードが見えてきました。ファッションではおなじみの迷彩柄と、トレンチコートが並んでいますね。
O:迷彩柄は二度の世界大戦のなかで普及しました。戦争を象徴し、周囲に隠れ、溶け込むことを目的として考案されたデザインですが、たとえばジョン・ガリアーノによるクリスチャン・ディオールの作品では、ゆったりとトレーンのひく優雅なイヴニング・ドレスへと転用され、はっきりとその存在感を示しています。

T:あまりにも美しいデザインなので、もはや、迷彩柄が戦闘服に使われているということを忘れてしまいますね。トレンチコートも軍服が出自なんですよね。元々の用途や意味が、デザイナーによってガラッと変わる代表的な例かもしれません。 次のコーナーは撮影OKなのでインスタグラムなどでかなりアップされていて、注目している方も多いのでは。
F:そうですね、多くの方が、コムデギャルソンの衣装にも注目していますが、私はこのコーナーではシンディ・シャーマンの作品に注目してほしいです。
というのもこの作品は「06. 教養は身につけなければならない?」というコードをよく表している作品だと思うんです。この作品では作家自身が、華美なドレスや宝石を身に着けて、厚化粧をし、肖像画然として画面に収まる上流階級の女性に扮しています。よく見ると隠し切れないシワやたるみも残酷に映し出されているんですよ。アートやファッションを表面的に取り入れ、人工的・表面的に取繕うことの脆さを表現しています。

T:彼女はさまざまな人物に扮したセルフ・ポートレイト写真によって、ステレオタイプを可視化することで知られていますね。確かに、シワまで細かに表現されているのが驚きです。
O:次のコーナーの「05. 見極める眼を持たなければならない?」では、「ロゴ」についてちょっと考えてみませんか。
かわいらしいモスキーノのクマがついていますね。でも、これは平面的なプリントで、周りには紙の着せ替え人形のような折り代がついています。スクリーンの二次元でしかファッションやモノをみようとしない、今の私たちの現状を批評している作品なんです。

T:なかなか奥が深いですね。「07. 服は意思を持って選ばなければならない?」にはシャネル・スーツなどが並んでいますが、福島さんがこのコーナーの中で「これ必見!」という作品はどれでしょう。
F:石内都さんの写真にぜひご注目ください。死後約50年を経たメキシコを代表するフリーダ・カーロの遺品を石内さんが撮影した作品を展示しています。フリーダは心身の痛みを抱えながら女性として情熱的な生涯を送り、力強い作品を描いていました。愛用の彩色されたコルセットやメキシコの民族衣装など、アイデンティティを模索した彼女の遺品から、フリーダの生きた痕跡が石内さんのフィルターを通して鮮やかに写し出されています。

T:石内さんは広島で被爆された方の衣服や、おきものの銘仙も撮影されていて、衣服にまつわる写真をたくさん撮っていらっしゃいますよね。
次のコーナーも写真作品ですね。
F:はい、オランダのアーティスト、ハンス・エイケルブームの作品《フォト・ノート》です。
T:同じような服装の人々がたくさん写っていますね。

F:同じ日に、同じ場所で撮影されているんです。よく見ると身に着けたアイテムによって類型学的にまとめられているのがわかります。各作品の下に記されたキャプションを見て驚くのは、そのほとんどが30分~2時間程度の間に撮影されていること。短時間の間にこれだけ似通ったコーディネートで歩く人々がいるという事実に、個性や着ることの自由について考えさせられます。

ハンス・エイケルブーム 《フォト・ノート 1992–2019》 1992–2019年 ©Hans Eijkelboom
T:個性を発揮したつもりでも、誰かと被ってしまう……。ということは何のためにおしゃれをしているのか、つまりは何のために服を着ているのか、考えてしまいますね。この展覧会を最も端的に表す作品かもしれません。「08. 他人の眼を気にしなければならない?」というコードがぴったりの作品だと思います。
続いてはずいぶんパンキッシュな衣装が並んでいます。「ツッパルな」というネオンサインが目を引きますね。
F:ここのコードは「09. 大人の言うことを聞いてはいけない?」です。元田敬三さんの写真作品には、自由を求めてツッパル若者や自分のスタイルを貫く人々が映し出されています。元田さんはカメラを持って街を彷徨い、独特のオーラを放つ人物に出会うと声をかけて撮影するというスタイルを続けているのですが、時々断られたり約束をすっぽかされたりすることもあるそうなんです。写真のひとつひとつには、彼らとの出会いが作家自身の言葉で綴られているのでぜひ読んでみてください。

T:エピソードを読むとクスッと笑ってしまうことも書かれていますね。ここは時間をかけてじっくり読み込みたいです。
さて続いて私たちが「ミックス」と呼んでいる「10. 誰もがファッショナブルである」のコーナーで小形さんが一押しの衣装はどれでしょう。
O:やっぱりアレッサンドロ・ミケーレによるグッチですね。贅沢な花柄とニューヨーク・ヤンキースのロゴが刺繍されたストールや、ロサンゼルス・エンゼルスの刺繍と漫画『ビバ!バレーボール』がプリントされた花柄のジャケットなどなど。さまざまな文化や宗教、性別や時代を越えて、ひとつの世界観をみせてくれているのが本当に面白いですよね。

T:すごい。いろんな要素が入っているのに破綻していない。さすがグッチ、といったところでしょうか。さて、壁に写っているこの映像はファッションショーの映像ですか?

Vetements(デムナ・ヴァザリア)ショー・ヴィデオ 2017年秋冬 Courtesy of Vetements
O:これは「11. ファッションは終わりのないゲームである?」に該当する作品で、ヴェトモンというブランドの2017秋冬コレクションの映像です。登場するのは37人のモデルたち。彼らにはそれぞれキャラクターがラベリングされています。私たちは他人の服装を通じて、その人に何らかの勝手なイメージを抱いてしまいますよね。これはそうした私たちが無意識に行ってしまうステレオタイプな見方そのものを、コレクションとして発表した批評的な作品です。
T:都築響一さんの強烈な写真群(その数150点!)のあるコリドールを抜けて、上の階に移動しましょう。今回は、いつもは所蔵作品を展示しているフロアにも大胆に展開していますね。


F:劇団マームとジプシー、演劇カンパニーのチェルフィッチュは、インスタレーション作品なので思い切って上フロアに展示しました。
T:演劇カンパニーによるインスタレーションって、なかなか見ることはできないですよね。美術館ならでは、ですね。いよいよ展覧会最後となりました。マームとジプシーのお部屋「11. ファッションは終わりのないゲームである。」を抜け、最後のお部屋に向かいましょう。どうやら暗くなっているようですね。「12. 与えよ、さらば与えられん?」のコードを掲げる部屋から何やら声が聞こえてきますね。

F:「服をもらえないですか。今着てるその服でいいです」というセリフが聞こえてきませんか? 誰かが私たちに問いかけてきます。
チェルフィッチュの映像演劇は舞台と観客席という関係を曖昧にして、新しい演劇の形を提示しています。映し出されている人物は輪郭がぼやけていますが、その問いははっきりと観客に向けられていますよね。「服がないんです」と迫ってくるシーンがあるのですが、私たちはそれに対して何ができるんでしょうか。そんなことを考える作品です。

チェルフィッチュ 《The Fiction Over the Curtains》 2017–2018年 precog蔵
プロダクションショット 撮影:加藤甫 ©chelfutsch, courtesy of precog
T:この作品を最後に、展覧会は最初の「裸」というテーマに戻っていくんですね。私たちは、明日、何を着るのか……じっくり考えたいですね。